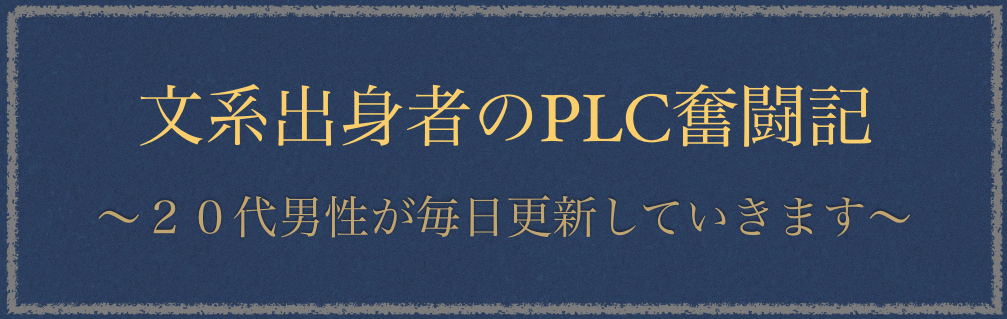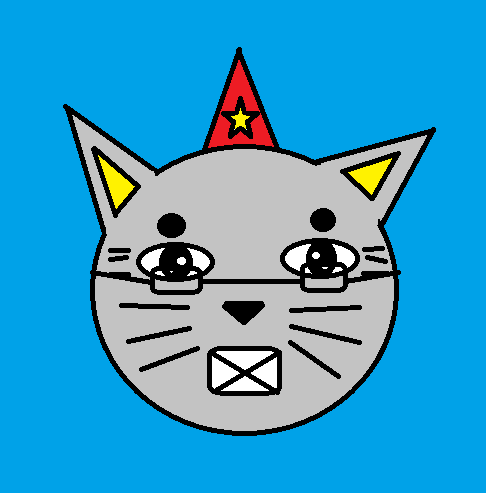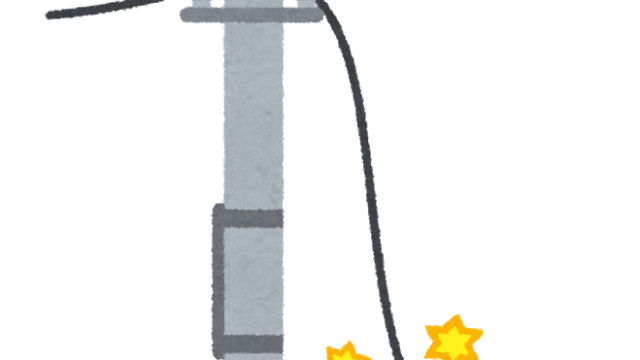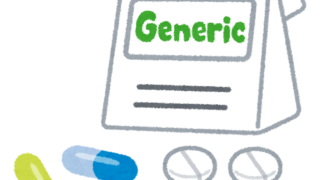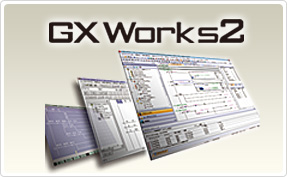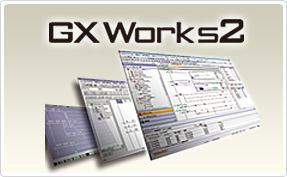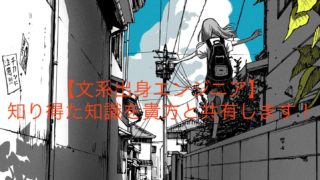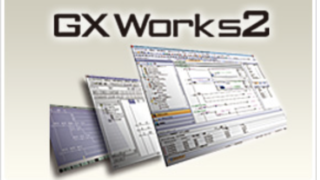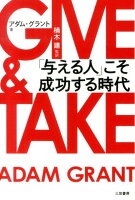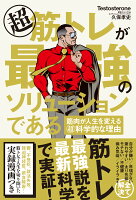関ジャニ∞の追加募集オーディションに行ってきたんですが
僕の隣に80歳を超えているであろう方が、審査員の爆笑をさらっておりました。
今回のメンバーオーディションはギャクセンを審査対象としているらしいです。
このままでは
落とされてしまいそうです・・・
続く
どうも僕です
今回は電気のお仕事をされている方なら出会ってしまうであろう
スターデルタ回路について一緒に学んでいけたらなと思います。
初学者の方でしたら
「ほほう。星の名前かね?」と
思われた方いますよね?いますね!
結論から説明させていただきますと
始動電流を三分の一にできるので配線&機器の節約になる
ってことです!
今回もよろしくお願いいたします。
スターデルタとは?

スターデルタなんて聞いたことないですよね?
僕もこの業界に入ってから知りました。冒頭でもお話ししましたが
始動電流を三分の一にしてくれる電気回路の組み方になります。
スターデルタ回路とは
Y-Δ変換(ワイ-デルタへんかん、Y-Δ transform)、スターデルタ変換(star-delta transform)、T-Π変換(ティ-パイへんかん、T-Π transform)とは、Y字型に接続したY接続(Y diagram)回路と、三角形に接続したΔ接続(Δ diagram)回路が、等価の回路になるように変換する手法である。回路の形状がアルファベットのY・Tやギリシア文字のΔに見えることからこの名前がつけられた。なお、イギリスではY接続回路をスター接続(star diagram)回路と呼ぶ。
一部の文献では、Y接続からΔ接続への変換をY-Δ変換と定義し、逆変換(Δ接続からY接続への変換)を、Δ-Y変換、デルタスター変換、Π-T変換と記載している。
始動電流を抑えないと、高電流が流れてくるので他の機器もそれに耐えられるものにしないといけない所を対策してくれるよー
正直この説明だとわかりませんよね?笑
僕の記事は基本的に触りさえ押さえればいいと思っているのでここでは
・始動電流を抑えてくれることで、ブレーカーや配線などを大きなものにしなくても良くなるため、配線コスト&機器コストの節約になる
・始動電流は3分の1に抑えられる
ってことを覚えておけばいいと思います。
始めだけ電流値抑えてあげて、一定時間後はスター回路→デルタ回路に切り替えてあげて通常の電流値で動作します
どんな所で使用するの?

どんなところで使用されているのか気になりますよね?
ここさえ押さえておけばいいので先に結論を書きますね
3.7kw以上の三相誘導電動機を始動するときに使用しないといけません。
電動機を始動するときに、初めは定格電流値の何倍もの電流が流れてしまいます。こうなると機器に対して負担になりますね。
また他の機器もその始動電流値のためだけに、機器の電流容量値もあげないといけません。
それだと制御盤も大きくなってしまいますし、配線作業もめんどくさいですよね?
なのでスターデルタ回路を使用してあげるということですねー
まとめ
どうだったでしょうか?
今回は簡単ですがスターデルタ回路をご紹介させていただきました。
要点をまとめると
・始動電流を抑えてくれることで、ブレーカーや配線などを大きなものにしなくても良くなるため、配線コスト&機器コストの節約になる
・直入れだと、始動時には定格電流の5~7倍もの電流値が流れてしまう。なのでスターデルタ回路にして、始動電流を3分の一に抑える
・3.7kw以上の三相誘導電動機を始動するときに使用しないといけません。
今回もありがとうございました。
良かったら他のブロガー様の記事もご覧ください。↓↓↓
おすすめ書籍